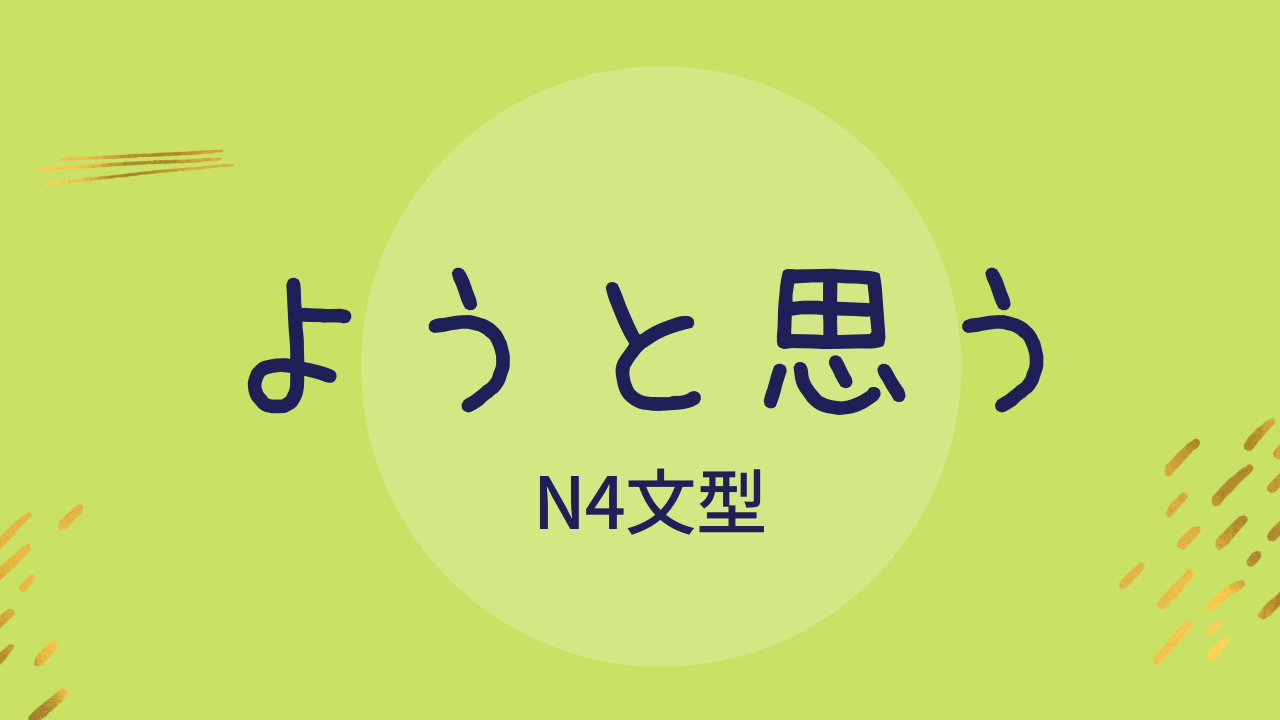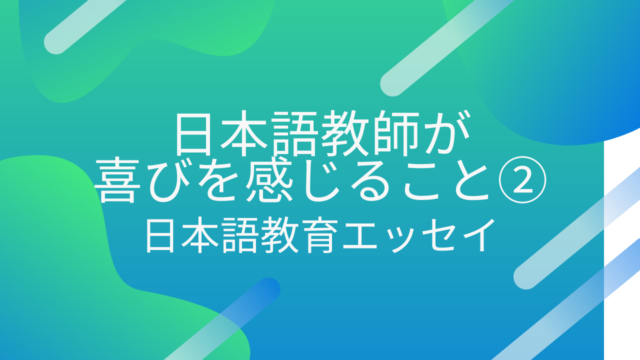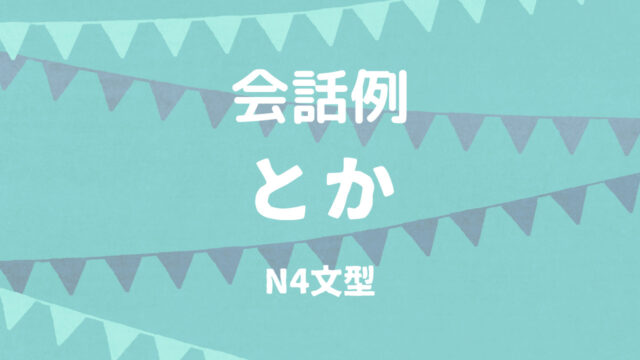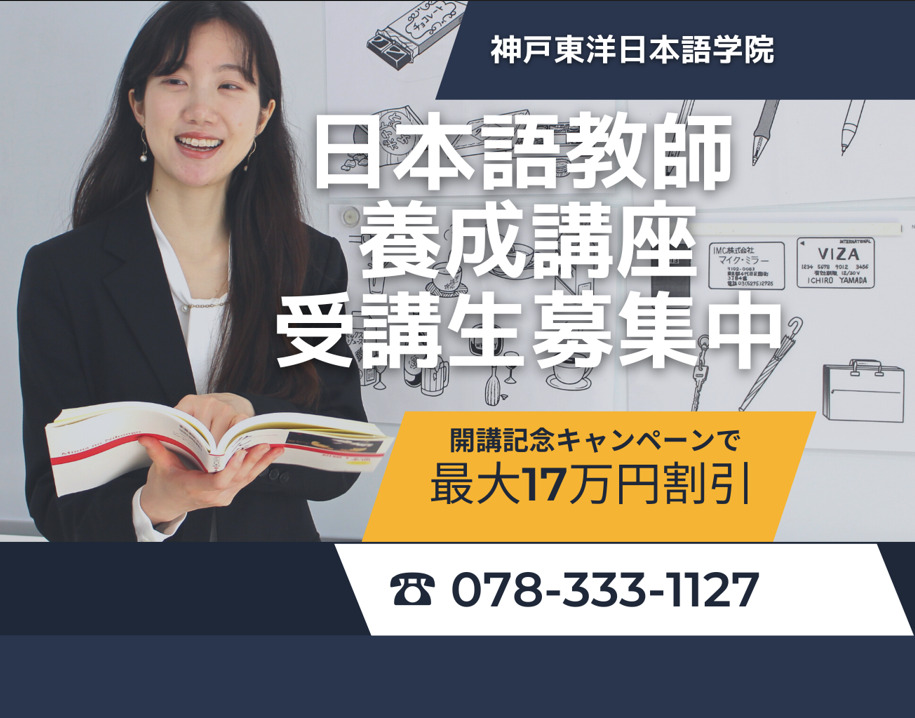みなさんおはようございます。
この記事では日本語専任講師歴7年以上の経験から、N1~N5までの文型の意味、使い方、前件後件のルール、よくある間違い、類似文型との比較などなど詳しく解説していきます。日本語学習者にはわかりやすく、日本語教育者には指導の参考になる記事を提供できるよう頑張りますので、是非最後までご覧ください。
今日の文型 「~ようと思う」
導入
使い方 自分の決めたことや計画を他の人に言う
・導入例①【私は夏休みに京都へ行こうと思っています。】
と言うことができます。
・導入例②【私は来月アルバイトを辞ようと思っています。】
・導入例③【今から店長に電話しようと思います。】
どうすればいいですか。
・説明
解説(日本語教師向け)
ここからは日本語教育者向けの解説をしていきます。
意味
・自分の意志や計画を他人に伝える
接続
V意向形+と思います
V意向形+と思っています
前件/後件のルール
・ルールA 自分で決められないことには使えない
「~ようと思う」は自分の気持ちや決めたことを他の人に伝えるときに使います。そのため自分の意志で決められないことに使うことはできません。
来月の大学入試に合格しようと思います。
・ルールB 主語が三人称の時は伝聞の表現が必要
「~ようと思う」は基本的に主語が一人称にしか使えません。しかし伝聞表現を使うことで主語が三人称の文でも使うことができます。
彼は来週京都へ行こうと思っています。
彼は来週京都へ行こうと思っているそうです。
伝聞表現:~そうです・~らしい・~って・~と聞いた・~と言っていた…
・ルールC 「ようと思いますか」は使わない
相手の意志や計画を確認するときに、「ようと思いますか」と聞きません。質問をしたいときは「~しますか」と聞きましょう。
注意点
・導入
①未来の予定を使って導入する
初めの導入は学習者の今後の予定を聞いてたり、自分の予定を言ったりと予定を使うとスムーズな導入ができます。未来の予定、計画で文型がある程度理解してから、意志決定が関わる例文を提示するのをお勧めします。
②「ようと思う」と「ようと思っている」の違いは学習者のレベルに合わせる
「ようと思う」と「ようと思っている」の違いは、学習者のレベルを見て説明をするかどうかを判断しましょう。初めての導入ではそこまで理解が進まない可能性があるので、違いまで説明すると混乱する恐れがあります。その場合はすべて「ようと思っている」を使って説明するといいでしょう。学習者のレベルが高い場合や、復習での追加説明など余裕がある場合は、しっかりと違いを提示し説明をしましょう。
学習者によくある間違い
・意志があまり関係のないことに使う(スケジュールなど)
今日は大学入試で名古屋に行こうと思っています。
入試で名古屋に行くことは、感情がない行動です。そのため「~予定」を使いましょう。
今日は大学入試で名古屋に行く予定です。
・他人やみんなで決めたことに使う
例:
私は来週出張で北海道へ行こうと思っています。
一般的には出張にいつ、どこに、誰が行くかは会社が決めることです。そのため社長など、自分で決められる立場ではない人が言うと、不自然な文になります。
私は来週出張で北海道へ行く予定です。
まとめ
・自分の意志や計画を他人に伝えるときに使う
・主語に二人称、三人称は使わない。(伝聞はすべてOK)
・基本的に質問の文には使わない
・自分で決められないことや他人が決めたことには使わない
以上「ようと思う」の解説でした。
「ようと思う」は類似文型である「~つもり」と合わせて勉強する文型です。”みんなの日本語”では同じ31課で勉強し、「ようと思う」を先に導入しています。教材によって前後は変わりますが、先に導入する文型をしっかり理解できれば、もう片方の文型の理解がスムーズになります。どちらも日常会話で耳にすることの多い文型ですので、しっかり定着できるよう指導案を考えましょう。
ここに書いてあること以外の疑問や質問はコメントをお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。