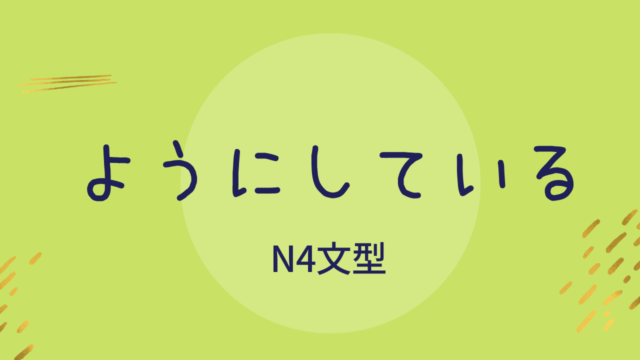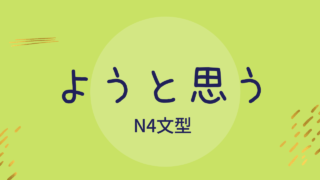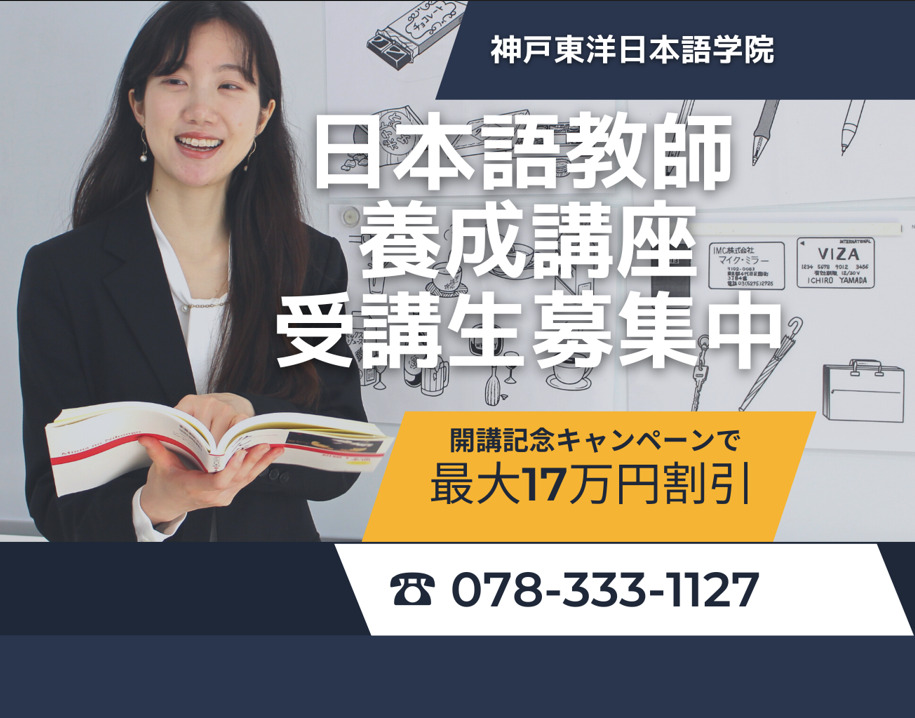みなさんおはようございます。
この記事では日本語専任講師歴7年以上の経験から、N1~N5までの文型の意味、使い方、前件後件のルール、よくある間違い、類似文型との比較などなど詳しく解説していきます。日本語学習者にはわかりやすく、日本語教育者には指導の参考になる記事を提供できるよう頑張りますので、是非最後までご覧ください。
今日の文型 「~かた」
導入
使い方 自分の決めたことや計画を他の人に言う
・導入例①【おいしい天ぷらの作り方がわかりません。】
・導入例②【きっぷの買い方を教えてください。】
・説明
「Vマス形+かた」と覚えましょう。
解説(日本語教師向け)
ここからは日本語教育者向けの解説をしていきます。
意味
・~をする方法
接続
Vマス形+かた
前件/後件のルール
・ルールA 無意志動詞は使えない
「~かた」に接続する動詞は意志動詞だけです。無意志動詞には使えません。
無意志動詞:わかる、疲れる、始まる、晴れる、咲く、売れる…
注意点
・導入
①「~かたがわかりません」を使って導入する
「~かた」の導入では学習者がやり方を知らないこと、できないことを使って場面設定をすると説明が簡単です。また、「~かたがわかりません」や「~かたを教えてください」は、学習者が初級レベルの会話で必要な文法、使い方です。そのため導入からよく使う場面設定で定着できるようにしましょう。
・Ⅲグループ 〇〇します→○○のしかた
「~かた」の接続は基本的に「Vマス形+かた」です。シンプルな接続なので、学習者の間違いも少ないかと思います。しかし、Ⅲグループの”○○します”だけは特別な接続になるので注意が必要です。
Ⅲグループ 勉強します+かた ⇒ 勉強のしかた
学習者によくある間違い
・助詞 を→の に変えるのを忘れる
「~かた」の文を作るときに、前の助詞が変わることを知らない学習者や忘れてします学習者が見られます。学習者には「を+V」が定着しているので、「の+Vかた」に変わることが定着し難くなっているようです。
私は料理を作り方がわかりません。
私は料理の作り方がわかりません。
学習者からどうして助詞が変わるかの質問があるかもしれません。しっかりと理解できる学習者には、「Vかた」は動詞ではなく名詞になると説明をしましょう。
・「~の来かた」 という使い方をする
「~の行きかた」というのはよく使いますが、日本人は「~の来かた」という使い方は基本的にはしません。
まず、使わない理由の一点目は”来る”という動詞は自分の立ち位置から見て、自分の立ち位置に到着することが前提で使います。そのため「来かたがわかりません。」だと、今どうやってそこに来たのかという矛盾が発生します。
では、「来かたがわかりますか。」という質問文はいいのではないかと、思う方がいると思います。確かに自分の今いる場所まで、来る方法という意味では間違っていません。しかし、実際このような場面で質問するときは「どこかわかりますか。」と質問することが普通です。そのため基本的に「~の来かた」という使い方はしないと説明して問題ありません。
Aさん、私の家までの来かたがわりますか。
Aさん、私の家がどこかわかりますか。
まとめ
・~する方法を聞くときに使う
・無意志動詞は使えない
・助詞が変わることに注意
・「~の来かた」という使い方を教えない
以上「~かた」の解説でした。
「~かた」は”みんなの日本語”では新出語彙として14課で勉強します。しかし日本語能力試験の教材では、N4文法として出てきます。”みんなの日本語”14課は動詞が増えるので、新出語彙が多くなかなか「~かた」の使い方を丁寧に説明する時間がありません。そのため簡単な文型ですが学習者に、あまり定着していないように感じます。現在特定技能や技能実習の来日者が増えていることから、N4の重要度が増しています。そのため簡単な文法ですが、しっかり理解し定着できるような、説明ができるようにしましょう。
ここに書いてあること以外の疑問や質問はコメントをお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。