みなさんおはようございます。
この記事ではN1~N5までの文型の意味、使い方、前件後件のルール、よくある間違い、類似文型との比較などなど詳しく解説していきます。日本語学習者にはわかりやすく、日本語教育者には指導の参考になる記事を提供できるよう頑張りますので、是非最後までご覧ください。
目次
今日の文型 「~ことができる」
導入
使い方① ~する能力がある
・導入例①【アリスさんはひらがなを書くことができます。】
・導入例②【アリスさんは自転車に乗ることができます。】
・説明
使い方② 場所や物で~ができる 状況から考えて~できる
・導入例①【コンビニでサッカーのチケットを買うことができます。】
・導入例②【スマホで写真を撮ることができます。】
・導入例③【ここでたばこを吸うことはできません。】
・説明
解説(日本語教師向け)
ここからは日本語教育者向けの解説をしていきます。
意味
①~する能力がある
②場所や物で~ができる 状況から考えて~することが可能だ
接続
V(辞書形)+ことができる
前件/後件のルール
・ルール① 無意志動詞は使えない
「~ことができる」に接続する動詞は意志動詞だけです。無意志動詞には使えません。
代表的な無意志動詞:わかる、疲れる、始まる、晴れる、咲く、売れる…
・ルール② 悪いことには使えない
結果が悪くなる文には使えない
例1:スピード違反をすると罰金を払うことができる。
例2:欠席すると出席率を落とすことができる。
例3:失敗したら罰ゲームを受けることができる
注意点
・導入
①初級者には場面設定を丁寧に
初級者には「名詞+ができます」を使って導入するのが基本になります。
使い方①は学生のできることを事前に把握しているとスムーズな導入ができます。
使い方②はコンビニやスマホなどいろいろな例文を作れる場面設定がおすすめです。
使い方②の状況については、同じ場所/もので、できる時とできない時を提示するとわかりやすくなります。
②初中級者は導入はシンプルに(特に漢字圏の学生)
初中級者や漢字圏の学生は「能力」「状況」「条件」などの言葉を理解できます。
そのため場面設定よりも、先に言葉で意味を説明する方がスムーズに導入できます。
・否定「ことはできません」 助詞の確認
肯定の形では「ことができません」と助詞は「が」ですが、否定の形になると「ことはできません」と助詞が「は」に変わります。意外とこの助詞の変化を見落としている人が多いです。導入、練習から定着できるよう強調しておきましょう。
学習者によくある間違い
・誰にでもできることに使う
例1:
私は勉強することができます。
勉強することは誰でもすることができます。そのため能力にはなりません。
私は一日8時間勉強することができます。
時間を入れることで、他の人より長い時間できるという能力になるので問題ありません。
例2:
私はご飯を食べることができます。
ご飯をたべることは誰でもすることです。そのため能力になりません。
私はご飯を5杯食べることができます。
5杯を入れることでほかの人よりも多く食べるという能力になります。
・場所/ものがメインですることに使う
例1:
携帯電話で電話することができます。
携帯電話のメインの機能は電話です。そのため「ことができる」は使いません。
携帯電話でゲームで遊ぶことができます。
例2
学校で勉強ができます。
学校は勉強する場所なので、「ことができる」は使いません。
私の学校では、日本経済を勉強することできます。
他の学校ではできないこと。自分の学校で特別に勉強できることには使えます。
まとめ
・使い方は2つある ①能力②状況条件
・接続は意志動詞だけ
・悪い結果には使わない
・否定の形は助詞に注意
以上「~ことができる」の解説でした。
初級文法ですがこの後勉強する「可能形」のために大切な文型です。学生のレベルに合わせて解説を活かしていただければと思います。
ここに書いてあること以外の疑問や質問はコメントをお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。

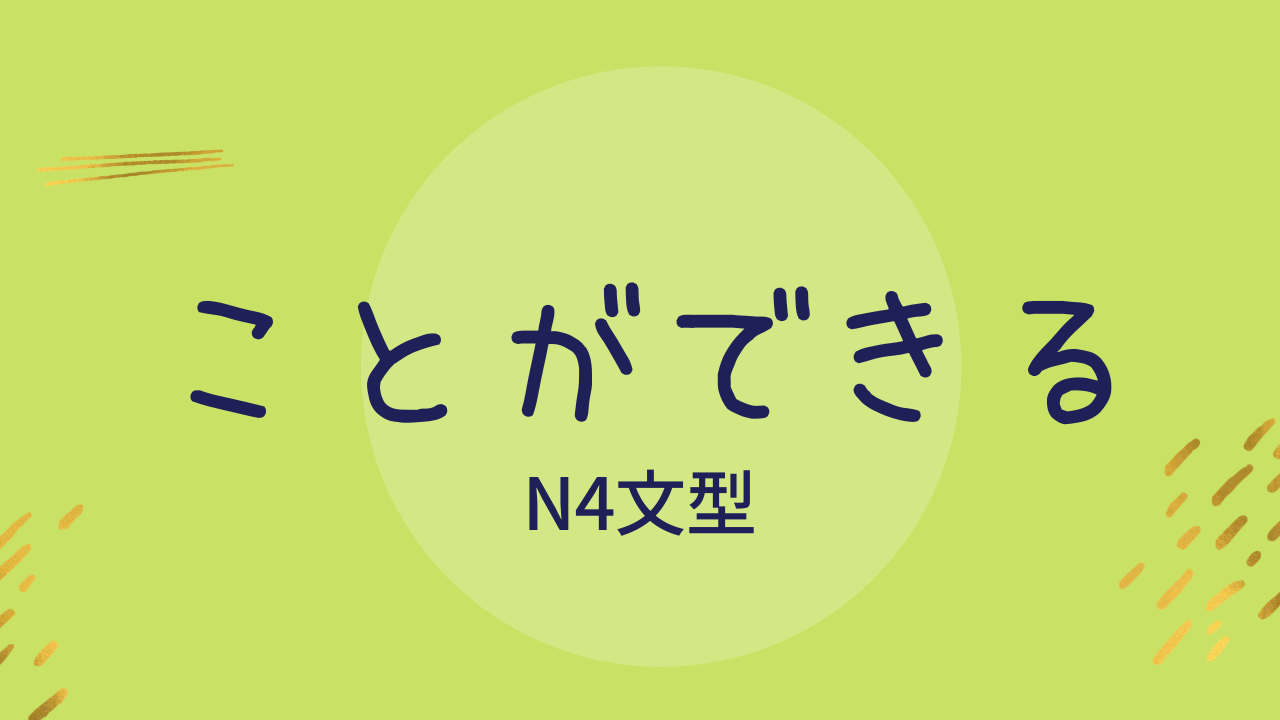


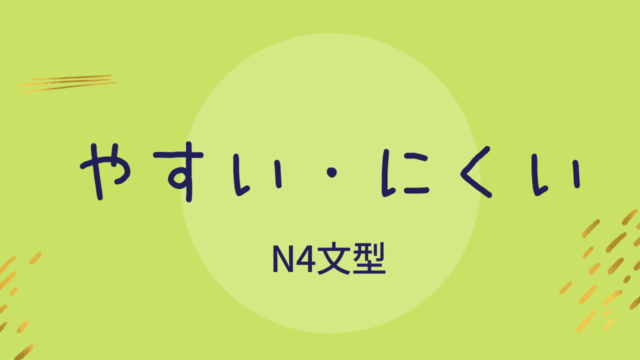
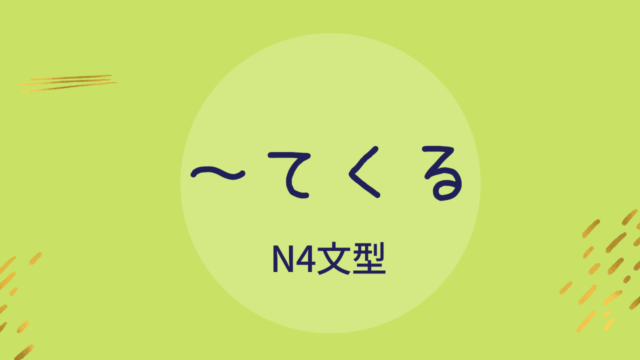
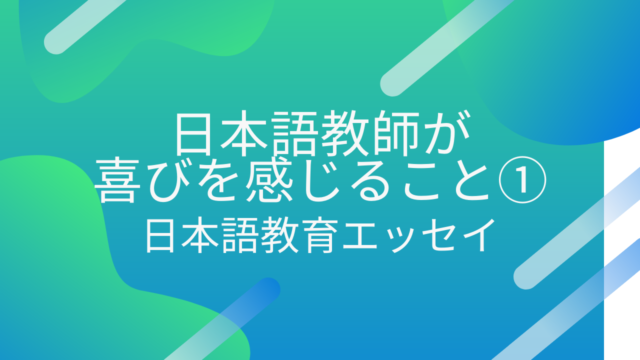



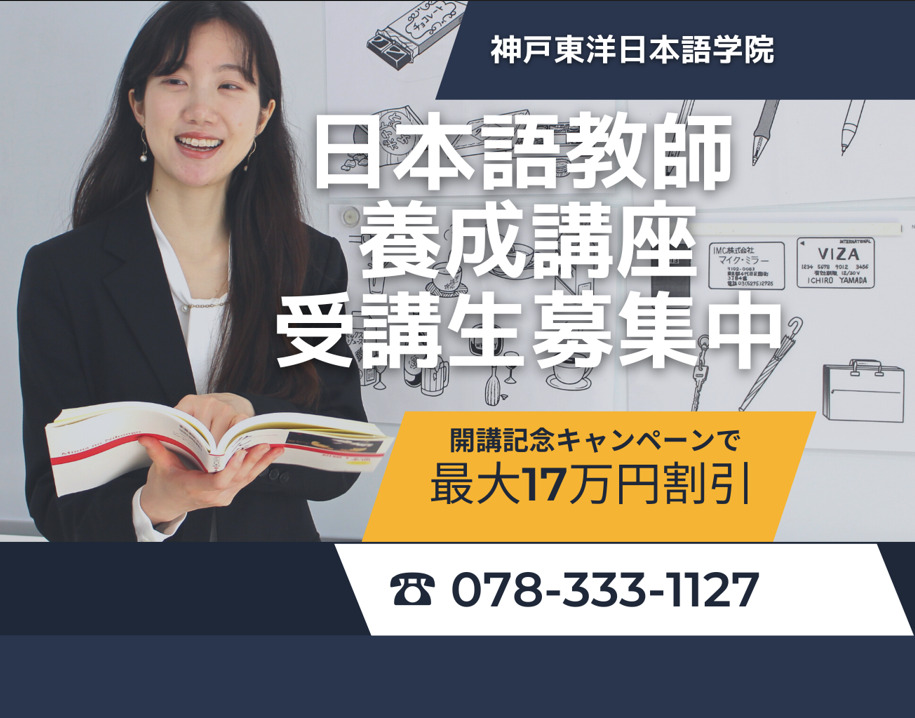
先生、質問があります!
否定の形は、助詞「は}を変えなければなりませんか。
よろしくお願いいたします。